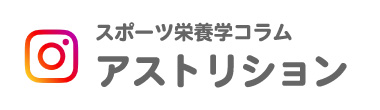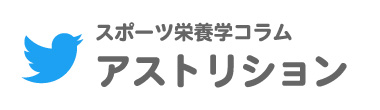離乳食に意識して取り入れたいのが鉄分です。
生後6ヶ月ごろからは、お母さんのお腹の中で蓄えていた鉄が少なくなる時期なので、赤ちゃんが貧血にならないよう、しっかりと鉄分を摂る必要があります。
鉄分は肉や魚などが主な補給源になりますが、野菜からもしっかりと取り入れることが大切です。
今回は、離乳食に使える鉄分の多い食材や吸収率を上げるポイント、レシピについて、管理栄養士が解説します。
目次
離乳食に使える鉄分が多い野菜
離乳食に使える鉄分が多い野菜は、小松菜やほうれん草などがあります。
野菜の中でも鉄分が多いのは、色の濃い「緑黄色野菜」といわれる野菜です。
緑黄色野菜には、鉄分だけでなく、鉄分の吸収を助けるビタミンCも含まれるため、効率的に補給できます。
離乳食に使いやすい鉄が豊富な野菜の種類と、鉄分の含有量を下記の表にまとめました。
| 野菜名 | 1食あたりの量 | 鉄分の含有量 |
| 小松菜 | 10g | 0.28mg |
| サラダ菜 | 10g | 0.24mg |
| グリンピース (ゆで) |
10g | 0.22mg |
| かぶの葉 | 10g | 0.21mg |
| 水菜 | 10g | 0.21mg |
| ほうれん草 | 10g | 0.2mg |
| サニーレタス | 10g | 0.18mg |
| 春菊 | 10g | 0.17mg |
| ブロッコリー | 10g | 0.13mg |
1日2回食以上になる離乳食中期(生後7~8ヶ月ごろ)は、1日1回以上は色の濃い野菜をあげられるとよいでしょう。
鉄分が多い野菜と組み合わせたい食べ物
鉄分が多い野菜を取り入れるのと合わせて、次に紹介する食べ物も意識して取り入れるようにしてみましょう。
ビタミンCを含む食べ物
野菜に含まれる鉄分は「非ヘム鉄」といい、肉や魚に含まれる「ヘム鉄」に比べると吸収率が低くなっています。
非ヘム鉄は、ビタミンCと組み合わせることで吸収率が高まります。
野菜はもともとビタミンCを含みますが、離乳食では加熱によりビタミンCが減ってしまうため、ビタミンCが豊富な野菜も意識して取り入れるとよいでしょう。
【ビタミンCを含む食べ物】
| 食べ物名 | 1食あたりの量 | ビタミンCの含有量 |
| パプリカ(赤) | 10g | 17mg |
| パプリカ(黄) | 10g | 15mg |
| ブロッコリー | 10g | 14mg |
| カリフラワー | 10g | 8.1mg |
| 水菜 | 10g | 5.5mg |
| キウイフルーツ (ゴールド) |
10g | 14mg |
| キウイフルーツ (グリーン) |
10g | 7.1mg |
| 柿 | 10g | 7mg |
| いちご | 10g | 6.2mg |
| オレンジ | 10g | 6mg |
鉄分をさらに強化できる食材
野菜の非ヘム鉄だけで必要量を満たすのは難しいため、ほかにも鉄分が豊富な食べ物を取り入れることが大切です。
離乳食に取り入れやすい食べ物は下記があります。
【野菜以外の鉄分を含む食べ物】
| 食べ物名 | 1食あたりの量 | 鉄分の含有量 |
| 納豆 | 15g | 0.5mg |
| 木綿豆腐 | 30g | 0.45mg |
| 豆乳 | 30g | 0.36mg |
| きなこ | 小さじ1(2.5g) | 0.2mg |
| かつお | 15g | 0.32mg |
| まぐろ | 15g | 0.14mg |
| ツナ缶(水煮) | 15g | 0.09mg |
| あさり | 15g(5粒) | 0.57mg |
| 豚レバー | 10g | 1.3mg |
| 鶏レバー | 10g | 0.9mg |
| 牛レバー | 10g | 0.4mg |
| 牛もも肉 | 15g | 0.2mg |
| 豚ヒレ肉 | 15g | 0.14mg |
| 全卵 | 1/3個 | 0.27mg |
| オートミール | 大さじ1(7g) | 0.27mg |
大豆製品、魚、肉、卵、オートミールなどに多く含まれるため、先ほど紹介した野菜と組み合わせて取り入れるようにするとよいでしょう。
赤ちゃんの1日に必要な鉄分はどのくらい?
生後6~11ヶ月ごろの赤ちゃんの1日に必要な鉄分は、下記のとおりです。
【1日あたりの鉄の推奨量】
| 男児 | 5.0mg |
| 女児 | 4.5mg |
鉄分が豊富である小松菜の鉄分は、10gあたり0.28mgであることを考えると、推奨量を満たすのはなかなか大変な数字であることがわかります。
しかしこの推奨量は、鉄分の吸収率が15%である場合の数値であることと、大人の吸収率を用いた数字であることから、赤ちゃんに適した数字とは言いづらくなっています。
なるべく充足したい量ではありますが、目安の量として考える方がよいでしょう。
鉄分不足に特に気をつけたいのは、母乳育児の場合です。
母乳には鉄分がほとんど含まれないため、育児用ミルクの場合に比べ、離乳食から積極的に摂らなければいけません。
【100mlあたりの鉄分の量】
| 育児用ミルク (13.5%調乳) |
0.88mg |
| 母乳 | 0.04mg |
母乳育児の場合でも、離乳食に育児用ミルクを取り入れるようにすると、手軽に鉄分を補給できますよ。
他にも、鉄分が強化されたフォローアップミルクや、赤ちゃん用の栄養強化食品なども上手に取り入れるとよいでしょう。
鉄分をたっぷり摂れる離乳食レシピ
先ほど紹介した食べ物を使った、簡単に作れて鉄分を摂れる離乳食レシピを紹介します。
鉄分不足に気を付けたい離乳食中期から、後期、完了期までの3レシピを紹介するため、ぜひ参考にしてみてください。
【中期(生後7~8ヶ月ごろ)】ツナとブロッコリーのトマトがゆ

鉄分を含むツナとブロッコリーをあわせたおかゆです。
トマトを加えることで、味と彩りのアクセントになってくれます。
<材料(1人分)>
・7倍がゆ 50~80g
・ツナ缶(水煮) 10g
・トマト(皮と種を取ったもの) 10g
・ブロッコリー(穂先) 1房分(5g)
<作り方>
1)ツナ缶はほぐす。トマトは皮と種を取り、細かく刻む。ブロッコリーはやわらかく茹でて穂先を刻む。

2)耐熱容器に7倍がゆを入れ、ツナ缶、トマト、ブロッコリーを混ぜて電子レンジ(600W)で40~50秒、おかゆがふつふつとするまで加熱する。
<ポイント>
ブロッコリーは冷凍のものでも可能です。電子レンジで解凍してから刻んで使いましょう。まとめて作って冷凍保存も可能です。1週間を目安に使い切ってください。
<栄養成分値>
エネルギー45kcal 鉄0.2mg
【後期(生後9~11ヶ月ごろ)】かぼちゃときな粉のオートミールおやき

鉄分補給にぴったりなオートミールと、きな粉を使ったお焼きです。
かぼちゃの自然な甘みで赤ちゃんも食べやすく、手づかみ食べにもおすすめです。
今回は、鉄分が強化されているきな粉味の「スクスクダイズ」を使用しています。

きな粉と同じように使えるため、離乳食にも取り入れやすいですよ。
普通のきな粉の8.3倍もの鉄分が含まれ、小さじ1杯(2.5g)で1.79mgの鉄分を補給できます。
<材料(2個分)>
・オートミール 大さじ1(7g)
・冷凍かぼちゃ 1個分(皮を取った状態で30g)
・牛乳 大さじ1
・スクスクダイズ(きな粉) 小さじ1
<作り方>
1)オートミールに牛乳をかけ、5分ほどふやかす。
2)冷凍かぼちゃは耐熱皿に入れ、水小さじ1(分量外)をかけ、ふんわりとラップをして電子レンジ(600W)で50秒~1分ほど加熱する。
3)かぼちゃの皮を取りフォークなどでつぶし、オートミール、スクスクダイズと混ぜ合わせる。

4)手で2等分に丸め、薄く油を敷いたフライパンで、両面に焼き色がつくまで弱火で焼く。

<ポイント>
多めに作って冷凍もできます。1つずつラップに包み袋などに入れて冷凍します。解凍は電子レンジ(600W)で30~40秒ほどです。1週間程度を目安に食べきりましょう。
<栄養成分値>
ふつうのきな粉の場合:エネルギー67kcal 鉄分0.6mg
スクスクダイズの場合:エネルギー67kcal 鉄分2.2mg
【完了期(生後12~18ヶ月ごろ)】小松菜のレンジオムレツ

赤ちゃんが食べやすいオムレツは、電子レンジで簡単に調理できます。
鉄分たっぷりの小松菜はちょっと苦味があり赤ちゃんが苦手な野菜ですが、卵が食べやすくしてくれますよ。
<材料(1個分)>
・卵 1個
・小松菜(葉の部分) 10~15g
・牛乳 大さじ1
・粉チーズ 1振り
・ケチャップ 少々
<作り方>
1)卵は溶きほぐし、牛乳、粉チーズを混ぜ合わせる。小松菜はやわらかくゆで、水気を絞って葉の部分を細かく刻む。

2)丸く深さのある耐熱容器にラップを敷き、溶き卵と小松菜をあわせる。

3)電子レンジ(600W)で30秒加熱し、一度取り出して箸でかき混ぜる。

4)再度40~50秒加熱し、ラップに包んだままオムレツの形に整える。

5)1~2分置いたらラップを外し、お好みでケチャップをかける。
<ポイント>
電子レンジにより加熱時間が異なるため、様子を見ながら加熱してください。小松菜は電子レンジでも調理できます。耐熱容器に小松菜と水を少々入れ、600Wで1分ほど加熱すればOKです。
<栄養成分値>
エネルギー95kcal 鉄1.3mg
離乳食に鉄分豊富な野菜や食べ物を取り入れて貧血を防ごう!
赤ちゃんの貧血予防には、離乳食の工夫がとても大切です。
なかなか離乳食が進まない場合でも、育児用ミルクやフォローアップミルク、栄養補助食品も上手に活用して鉄を補給しましょう。
レシピにも登場したスクスクダイズは、離乳食の時期はもちろん、幼児食の時期でも鉄分やカルシウム補給に大活躍してくれます。
赤ちゃんの鉄分を手軽に補給したい方は、ぜひ下記からチェックしてみてくださいね。
参考文献
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」
厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」